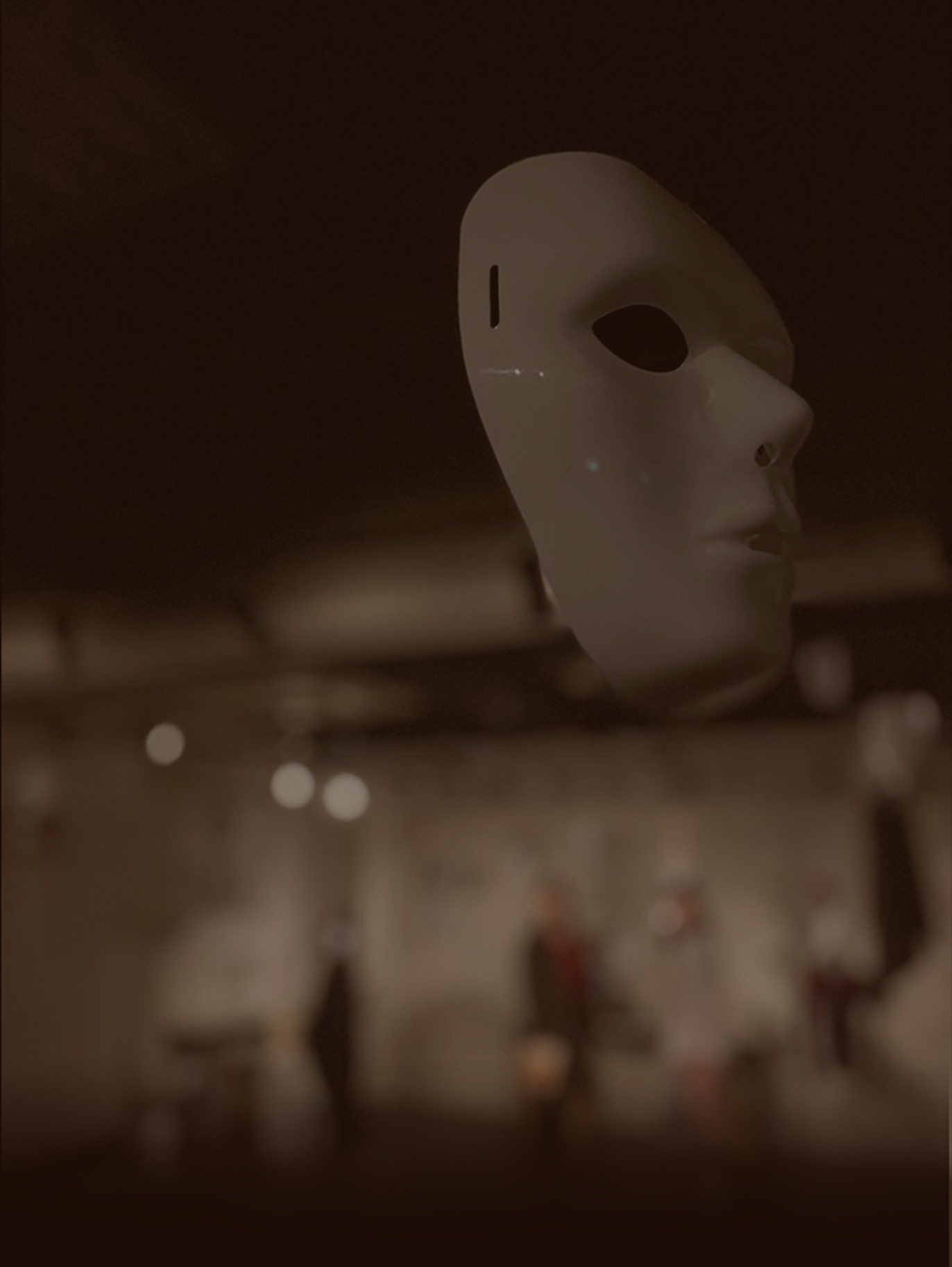令和座第9回公演『覚醒 -Awakening-』劇評
『浅間伸一郎に読売演劇大賞を獲らせるための文章』
公社流体力学(10代目せんがわ劇場演劇コンクールグランプリ、演劇レビュアー)
今回、令和座の『覚醒 -Awakening- 』の批評を書いてくださいと依頼が来たのでこの文章を書いているが今から皆様が読むのは批評ではない。
これは檄文だ!
読売演劇大賞と言えば演劇の上演を対象とする賞では日本最高の栄誉、と一部では言われているが小劇場の姿はほぼない。
世の中には読売演劇大賞(日本一の演劇)にふさわしい小劇場演劇が数多くあるにもかかわらず彼らは小劇場と言うだけで見向きもしない。
何故、こんな始まりかと言うと2024年の演劇においてその栄誉、特に最優秀演出家賞にふさわしい男こそ令和座主宰、浅間伸一郎なのである。
『覚醒』は間違いなく令和座と言う劇団において『大麻を吸おうよ』に匹敵するかそれ以上の最高傑作。こと演出においては令和座と言うだけでなく2024年最高の演出と言える。
にも拘らず、は見向きもされなかった。
この文章は読売演劇大賞にふさわしい男・浅間伸一郎を来年以降の読売演劇大賞で堂々と候補にすべく、眠たい演劇界を覚醒させる檄文である。
令和座というのは場の劇団である。
筆者が過去に見た作品は全て会場となる空間の特徴をを生かした作品作りであった。
しかし、実のところ演出自体はその空間でしかできない物でも戯曲自体は(アレンジは必須だが)他の劇場で上演しようと思えばできる。それは演劇において当たり前の事であり、欠点ではない。
しかし、『覚醒 -Awakening- 』はその壁を超えた。つまり会場であるときわ座でしか上演することができない作品となっている。
ときわ座は築50年以上の元生花店の2階建て木造家屋を利用したイベントスペースであり、中に入るとすぐにコンクリートの土間が広がり、すぐ目の前には縁側のような段があってお茶の間がそこにある。
そして客席中央の天井が壊され吹き抜けとなっており吹き抜け周辺の2階の様子が客席から見ることができる。
ときわ座を使う劇団は勿論、この特殊構造を利用するが客席が1階であることから、吹き抜け周辺で演技をするにとどまっていた。中には観客を2階にあげるという手法で2階を利用した団体もいた。
しかし、浅間は、1回から2階は吹き抜け周辺しか見えないという構造を
逆手に取り音の演劇を作り出す。
見えない代わりに足音を多用し、階段を登る音、2階の廊下を歩く音、怒った兄が勢いよく床を踏み鳴らす轟音。
その音だけで人物の感情を表現する。
勿論言葉を使わず表現するということでは無言劇などを実践している団体はいるが、この作品ではときわ座の廊下の遠近を利用して、吹き抜けの周辺で音がする、2階の廊下の奥で音がすると使い分ける。あなた2階の廊下奥なんて観客には全く見えないのに足音(時おり声)だけで一体何が起きているか容易に想像出来るんですよ!
そして、その音が築50年の木造家屋に反響して会場中に響き渡る。
そして普通の劇場じゃ物理的に足音の遠近を利用できない。2階の足音を1階届けられないし、舞台の裏側ではわざとらしい足音を出さないと音が届かない。この足音演劇はときわ座という特殊空間でしかできないのだ。
今、日本の演出家でここまで完璧に会場を舞台装置を超えた小道具として演出及び戯曲に溶け込ませられる人間がどれほどまでいるのだろうか。
また、ときわ座が駅の近くであり普通の劇場ではなく一軒家だからこそ駅前で兄が騒動を起こしてそれで警官が訪ねてくるという展開により生々しいリアルさを付け加えることが出来ている。
勿論それだけでなく、浅間の旧来の持ち味だった個性も爆発している。
元々奇妙な世界観を長い“間”を生かしたスローテンポな演劇で作り出していた。今作品も引きこもりの兄と妹・叔父を巡る家族の確執の話。と言う題材で間を使って緊迫感を作り出したと思いきや、いきなり日本刀持って追い掛け回したり(この際に、2階吹き抜け周辺でドタバタの追いかけっこをしたあと1階に逃げてくるという、緊迫感を1階2階を使い分ける上手さ)。妹が叔父を人質を取った場面では、兄が階段を下りてくる際のギシギシ音によって、兄がカオスな展開になっている1階に降りてくる、この場面で兄はどう動くんだという期待を高める。そして間を利用してからの面白さを爆発させていた。
そしてこの戯曲がここでしか成立しないのは、物語の結末を客席からは全く見えない2階廊下奥での足音と物音だけで成立させる。ここを言葉でやってしまったら作り上げていた異様さが崩れてしまう。SEでやってもダメだ。
今この時この場所で出している音だからこそ、あの取り戻しのつかない悲劇として完成するのである。この戯曲は2階廊下奥の足音が響く会場でなければ成立がしない。
この作品をさらに傑作として高めたのが兄を演じる碓井英司の使い方。令和座では「UNDER GROUND PARTY」短編「UNDER GROUND BAR」に出演し長編では久しぶりの登場となった俳優。巨漢である彼は立っているだけで見事なインパクトだがそれを利用し決して喋らせない。
他の登場人物が言葉で個性を出す中で、言葉より雄弁な足音を使う作品において碓井のその佇まいが!虚ろなその目が!異様な存在感を出す。
あれだけ喋らない男がこんな足音を出すなんて、一体あの体の中にはどんな感情が渦巻いているのかと想像を掻き立てる。
勿論ただ碓井を使えばいいという訳でない。このインパクトを最小の動きで最大限引き出す演技演出の巧みさ。
監視カメラをおもむろに設置したり突如外に出る。そしてラストのあまりにも突飛のない行動も、過剰なまでに説明を派部隊不条理な行動も、碓井の演技一つで混沌を観客に納得させる。
演技・演出・戯曲が三位一体となった究極のカオス。言葉を一切使わずにこれを作り出すことが浅間伸一郎以外にできるだろうか。
いや、いない。
これが浅間伸一郎が現代演劇の特異点として読売演劇大賞にいかにふさわしいかの文章である。
読売ってこういうタイプの作品を評価する賞じゃないからと思ったそこのあなた、
現代演劇の最先端である令和座をぜひ見てください。見たことのない演劇を見ることができるはずです。
そして天才には日本一の名誉がふさわしいと思います。
ただ、見るたびに想像の斜め上を行くので、なるほど足音演劇の団体なんだと思って見に行くと『覚醒』とは全く違う形の演劇が出てくるとは思う。
だって令和座・浅間伸一郎のイマジネーションは我々凡人では思いつかない。皆で驚嘆しよう。